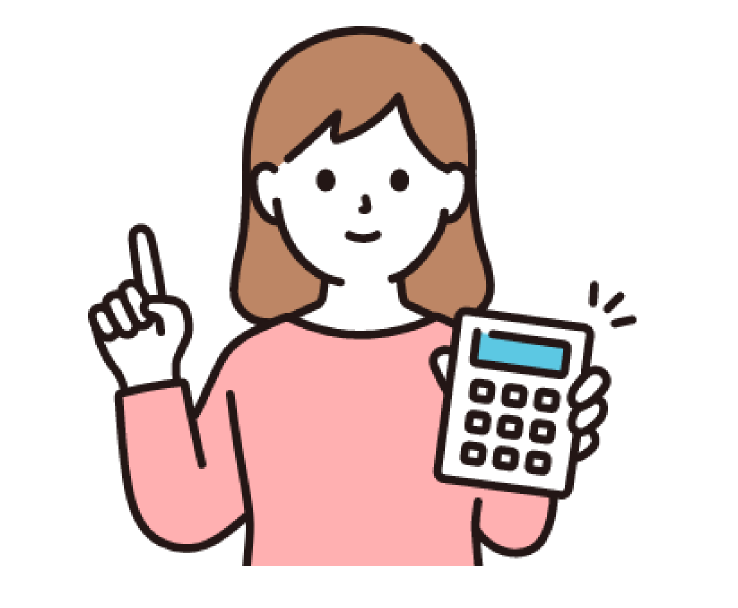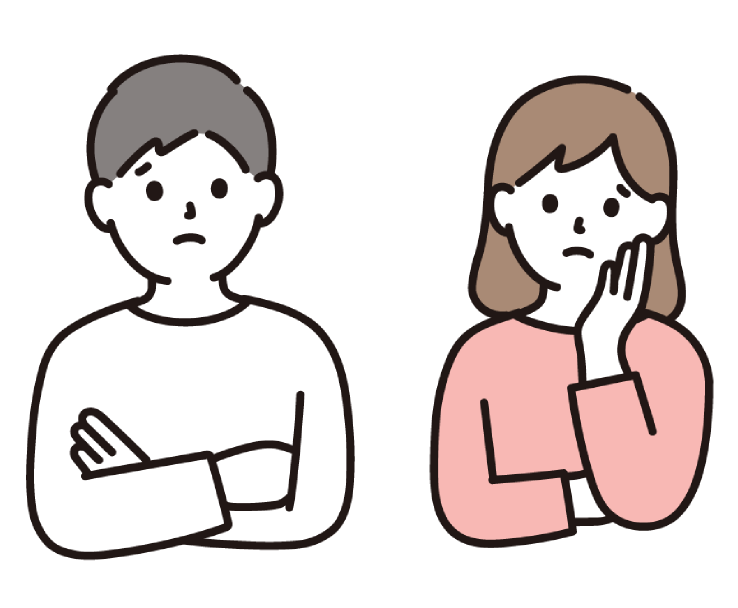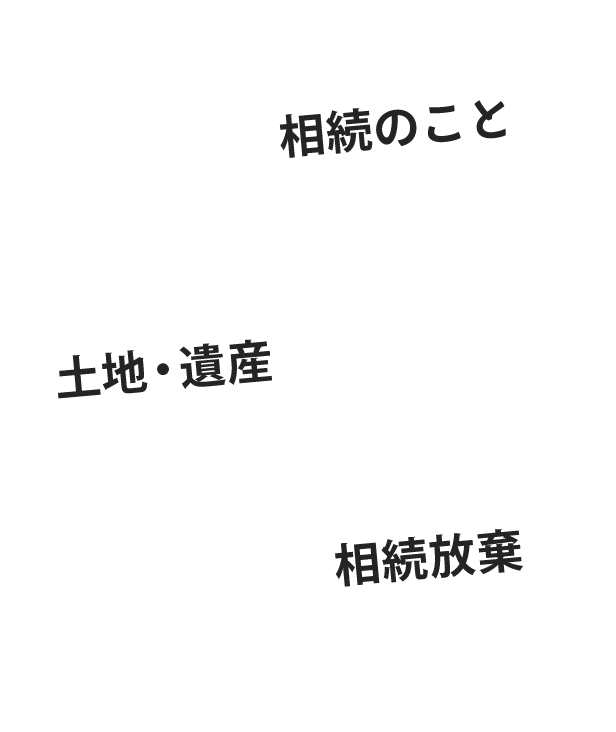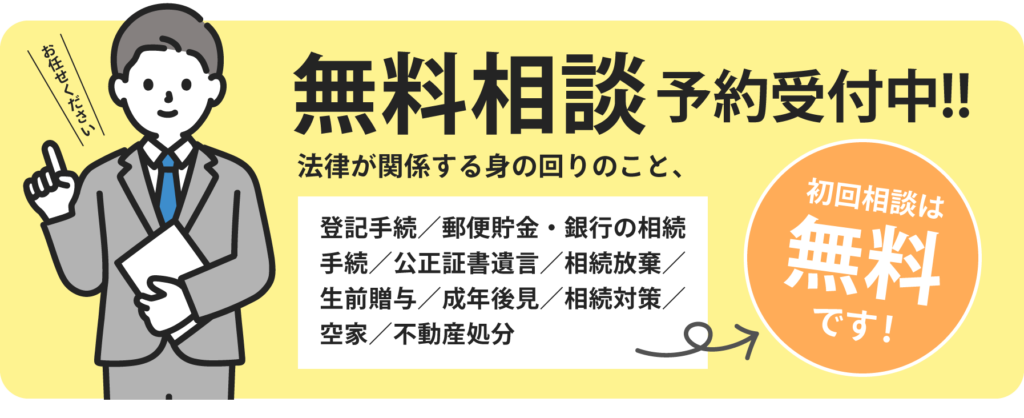相続登記(土地・建物等)
相続が発生し、土地や建物が相続財産の中にある場合には、相続人への名義変更の手続き(登記)が必要です。登記の手続きをしなければ、その土地や建物の名義人はずっと亡くなられた方のままです。
相続による土地や建物の名義変更の手続きに期限はありませんが、名義変更をしておかないと、売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません。
相続発生後、長期間名義変更の手続き放置していると、戸籍等の資料収集に手間がかかったり、次の相続が発生して相続関係が複雑となっていたり、相続人同士の話し合いが難しくなることもあり、名義変更の手続きを行うことが難しく、最悪のケースでは裁判にまで発展することもあります。相続が発生したら、なるべく早めに名義変更手続きをすることをお勧めします。
令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
土地や建物の名義変更は相続人全員で行います
『この土地は誰々のものに・・・』
『この建物は誰々のものに・・・』
といった具合で話し合いを行い決定していきます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書には下記が必要です。
・相続人全員が署名
・各自の実印での押印
なお、遺産分割協議をせず、法律に定められた相続人全員の法定相続分で登記をすることもできます。
※各自の持分についてだけの名義変更はすることができません。
名義変更手続き(登記申請)
1
相続人の調査・物件の調査
■戸籍の収集
亡くなられた方の本籍地の役場にて戸籍の収集を行います。
■物件の調査
亡くなられた方の名義になっている物件を、役場や法務局にて調査します。
2
遺産分割協議
相続権を有する人全員で、誰がどの物件を相続するのかを話し合います。
遺産分割協議が完了したら、その遺産の分割方法を遺産分割協議書にまとめます。
3
名義変更手続き(登記申請)
相続する土地や建物を管轄する法務局に対して、名義変更手続き(登記申請)を行います。
亡くなられた方の預貯金について
預貯金を引き出すための手続きをする必要があります。
金融機関に次の書類を提出し、手続きを行います。
預金を相続する手続き
まず、口座名義人が亡くなったことを金融機関に通知します。
すると、金融機関はその口座を凍結します。
凍結を解除するためには、金融機関の窓口に行ったり、郵送で次の書類を提出する必要があります。
・被相続人の口座の通帳やキャッシュカード
・金融機関で指定された届出書
・遺言書または遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・手続きをする人の身分証明書(運転免許証など)
必要な書類は金融機関や相続の状況によって異なるため、事前に金融機関に問い合わせが必要になります。
預貯金の相続の流れ
1
相続手続きの開始
相続発生時には、相続人が預貯金口座の情報を把握する必要があります。相続人は、預貯金口座の存在や金額、口座開設行などを確認するために、遺産調査を行うことが重要です。
2
相続財産の評価
相続財産は、相続人に分割される前に評価されます。預貯金口座の評価は、残高や利子などを考慮して行われます。評価が行われると、相続人の持分が計算されます。
3
相続税の申告
預貯金は相続税の課税対象です。相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に支払われる税金です。相続税の申告手続きでは、預貯金の金額やその他の相続財産の評価額を報告する必要があります。
4
相続分の確定
相続人が複数いる場合、相続分の分割が行われます。法定相続人や遺言書の内容に基づいて、預貯金の相続分が決定されます。相続分の確定後、相続人はそれぞれの持分を受け取ることができます。
5
口座名義の変更
預貯金の相続人が確定したら、相続人が預貯金口座の名義を変更する必要があります。銀行や金融機関に相続手続きの書類を提出し、預貯金口座の名義を相続人の名前に変更してもらうことが一般的です。
6
遺産分割の実施
預貯金などの相続財産が相続人に分割された後、相続人は自身の持分を受け取ることができます。これにより、預貯金口座の資金を引き出すことや、別の口座に移すことが可能になります。
農地整理について
農地の相続手続きは一般の土地の相続手続きとは異なり、農業委員会への届出が必要です。農地を相続し農業をする場合は相続税の納税猶予を適用できる可能性もあります。
このように、農地相続には通常の不動産相続とは異なる手続きや税金の計算方法があります。また、農地には法的制限があるため、売却や譲渡が難しい場合もあります。そのため農地を相続する際には、自身が農地を相続するのか手放すのかを慎重に検討する必要があります。
農地整理の流れ
1
相続者の確認
農地の所有者(被相続人)が亡くなった場合、まず相続者を確認します。相続人は法定相続人や遺言書によって指定される場合があります。
2
相続手続きの開始
相続人は、農地の相続手続きを開始するために、地方自治体の役所や農業委員会に相続届を提出します。届出書には相続人の氏名や関係、被相続人の農地の詳細などが含まれます。
3
相続税の申告
相続人は、相続税の申告を行う必要があります。相続税は農地の評価額に基づいて課税されます。農地の評価や減税措置に関しては、税理士や専門家の助言を受けることが重要です。
4
農地の管理
相続が確定した後、相続人は農地の管理を行う責任があります。農地の耕作や保全、農業活動の継続などが考慮されます。
5
農地の利用・処分
相続人は農地を自身で利用する場合や、他の人に貸し出す場合があります。売却や譲渡を希望する場合は、農地の利用制限や手続きに注意が必要です。